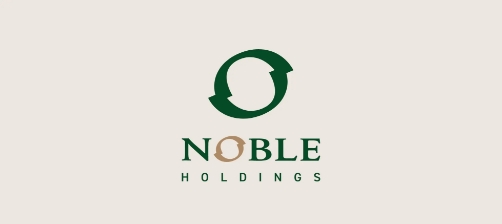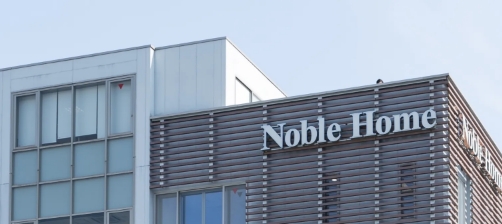多様性をチカラに変える人々を紹介するシリーズ
ノーブルホームの多様性ある人々をご紹介する連載【多様性をチカラに】。今回、対外企画の第二弾として取材させていただいたのは、株式会社サイタコーディネーションの代表取締役であり、自らコーチングスクールや幼児教室も主催されている、教育コーチング講師 江藤真規さん。前編では、アメリカでの生活を通してコーチングに出会ったエピソードをはじめ、江藤さんが考える多様性についてのお話を伺いました。
ティーチングとは違う「考えるきっかけ」がもたらす試行錯誤を通じて生きる力を高め、子どもたちの未来を開くコーチング、コーチングアプローチの魅力を、ノーブルホームのミッション「暮らしをひらく」と共にご紹介します。
教育コーチング講師 江藤真規さんのホームページはこちら
株式会社サイタコーディネーション
子育てへの悩みがコーチングと出会うきっかけに
今でこそ教育コーチング講師として活動していますが、はじめから「こういう仕事がしたい」と思って、コーチングを学んだわけではありません。私の場合、コーチングと出会ったきっかけは、子育ての悩みでした。
私たち家族は、転勤に帯同する形で7年間アメリカで過ごした経験があります。日本に帰ってきたのは、長女が小学校6年生、次女が4年生になった頃。幼少期をアメリカで過ごした子どもたちにとって、日本への帰国は非常に大きな変化だったはずです。ちょうど子どもたちが思春期を迎える年頃だったこともあり、私にとって今まで築いてきたものが砂の山となって崩れてしまうような、子育てや子どもとの関係性について非常に悩む時期でした。この状況をなんとかしなければと、すがるような思いで模索する中、出会ったのがコーチングです。
子どもとの関係性に悩んでいた私は、子どものためにとコーチングを学びはじめますが、いつの間にか自分のためにもなっていることに気が付きます。コーチングを学ぶ前は、関わる相手は子育てをしていく中で出会った友人が中心で、自分自身の世界はいつの間にか限定されていました。しかしコーチングをきっかけに自分の領域を広げ、「越境」して外に出てみることで、見聞きする話や自分を取り巻く世界が変わっていくのを実感しました。
はじめは、ビジネスコーチングを中心に活動していましたが、自分自身のキャリアと照らし合わせたときに、長く身を置いてきた子育ての領域でコーチングを展開していきたいという思いが強く、教育コーチング講師として活動するようになりました。
7年間の渡米生活で感じた「What do you think?」と尋ねる大切さ
コーチングとは、会話を通して相手の本当の気持ちを引き出し、相手の自発的な行動を促すことを目的としたコミュニケーションスキルのこと。先ほど、7年間アメリカで暮らしていたとお話ししましたが、実はアメリカのコミュニケーションの取り方は、コーチングのコミュニケーション手法と非常によく似ています。
例えば、日本で子ども同士がぶつかり合って喧嘩になったとき、日本では喧嘩を止めさせるためにまず我が子のことを叱るでしょう。けれどアメリカでは、まず「What do you think?」と聞きます。子どもたちがどうしたいのか、どうすればいいと思うのかを、子どもたち自身に考えさせる機会を重視しているからです。渡米したばかりの頃は、この子どもたち同士で解決に向かわせようとする姿勢に、カルチャーショックを受けました。
アメリカの子育ては、とにかく子どもを褒めます。日本には謙遜を美徳とする文化があるので、我が子を褒められたときに本人の目の前であっても「全然そんなことはないんですよ」と答えてしまう例が少なくないでしょう。けれどアメリカでは我が子の長所を全面に押し出すので、子どもたちが非常に自信たっぷりに育つのです。

さらに印象的なのが、子どもたちが幼いころからすでに社会の一員である、という意識を持っている点です。長女が通っていたピアノ教室で、ある子が「将来ピアニストになって、福祉施設でピアノを弾きたい」と夢を語っていました。自分の「好き」だけで完結せずに、その先に自然と社会との繋がりを意識し、公共の福祉に資する意欲を持っている。幼い頃から社会の一員として、自分自身に誇りを持って生きているのを強く感じました。
日頃から「What do you think?」と意志を聞かれ、一人の人間として対等に扱われていますので、渡米中に接した方はみな自分に誇りを持っていました。相手のいいところを引き出すコーチングへの理解を深めながら、7年間のアメリカ生活での出来事が再びよみがえってくるような感覚でした。学ぶために本を読むだけではなく、実際にその環境に身を置いて体感できたのは、私にとって非常に意義のあることだったと感じています。
すべてが言語化されない親子関係に、コーチングアプローチで関わっていく
コーチングは、実は馬車を意味する「コーチ」に由来する言葉です。レールのないところを走る馬車に例え、目標を持ったクライアントから「手伝ってほしい」と依頼を受けて、合意のもとに目的を達成するためのお手伝いをするのがコーチングです。けれど子どもから「こうしたい」「手伝ってほしい」という申し出は通常ありませんので、親子間で本来の意味でのコーチングは成立しません。
親子という近しい関係性であるからこそ、言語化されていないところまで寄り添い、傾聴と質問を重ねながら丁寧に引き出すアプローチが大切です。この親子間のアプローチについては、相手から「引き出す」というコーチング的な考え方に基づき、コーチングアプローチと呼んで区別しています。1人の人間として相手を尊重し、良い部分を認めて自己肯定感を高め、質問しながら相手の心の中にあるものを引き出していく姿勢が、親子間では特に求められているのです。

自分を知り、相手を知ることが多様性への第一歩
今回は多様性がテーマですので、私が考える多様性についても、少しお話ししていきましょう。「多様性」にはジェンダーや宗教、生まれ育った環境による違いなど、様々な要素が含まれます。その上で多様性とは何かと問われたら、私は1人1人が生き生きと暮らし、生きていくことが許される社会こそ、多様性が受け入れられた社会だと考えます。
例えば父親と母親と子ども、という一括りで考えがちな家族のあり方ですら、現代は多様性に満ちています。家族の姿として両親と子どもが自然とイメージされるように、まずは私たちが無意識に持っている思い込みに気付き、理解していくことも大切ではないでしょうか。
多様性とは決してすべてを平等にすることや、同じ権利を持っていると主張することではありません。1人1人が生き生きと自分らしく暮らしていくために、まずは自分自身の価値観の中にある思い込みに気付き、自分と他人の中にある違いを理解することが肝心です。
「こうでなければならない」と主張するのではなく、変化を受け入れ、時にはぶつかり合いやいざこざもしっかりと経験する。それらの経験を通して、他人と自分の意見の違いを認識することが、1人1人が生き生きと暮らす多様性のある社会につながると考えています。
次回、後編ではアメリカでの暮らしの中で出会ったファミリールームの考え方や、コーチングを通して考え得る住まいの重要性について伺います。